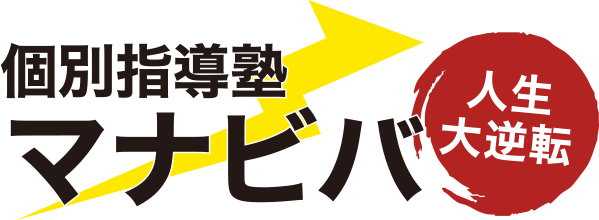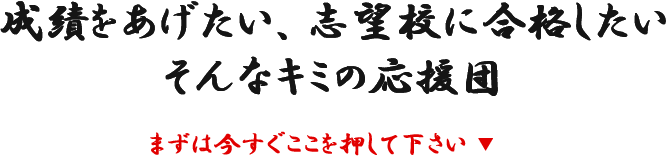大学には「文系」「理系」「芸術系」「文理融合型」など色々ありますが、全国でにありますが、最も多いのは「文系」です。
また、「国公立大学」と「私立大学」とでは、「私立大学」の数が勝ります。小さい私立大学もありますが、全体で学生数が多いのは私立大学です。
つまり、日本の大学では「文系の私立」に行く人が最多となります。
今回は、学生の中で多数派にあたる「私立文系」に着目し、その中で「地方」に所在地を持つ大学を探していきます。
しかしながら、全国中に「私立文系」の大学はあるものの、「どこの大学に行けばいいか、よくわからない」「もしオススメの大学があるなら、ぜひ教えてほしい!」などの声も沢山あることでしょう。
特に「地方」となると、都会の大学のようにメディアに度々出てくることがなく、地元の人たちだけがわかる学校が大半です。
それでは、「文系」で「私立」かつ「地方」の大学で、ココの学校に注目だ! というところをマナビバが調査し、ご紹介します!
学力の評価が高い地方私立大学(文系編)
<南山大学>

南山大学は愛知県の名古屋市に本拠を置く文系中心の総合大学です。中京圏・東海地区を地方に入れていいのか、という声は重々承知の上ですが、敢えて南山大学をご紹介します。
理由は、各地方の中核都市にもそれぞれ文系中心の総合大学はあるものの、やはり学力が高いと言えるまでのところに届いているのかがやや疑問だからです。
そこに南山大学の学力の高さを見るにつけ、ほぼ難関と言って差し支えないことから、いま一度、地方の代表格として取り上げました。逆に言うと、地方の文系大学は年々学力が低下していることの表れで、それだけ紹介するにもなかなか見つけられない、というのが正直なところです。
南山大学には、文系は人文学部、外国語学部、法学部、経済学部、経営学部、総合政策学部、国際教養学部の7学部があります。また理系では理工学部があり、合わせて8学部です。
特に女子の受験生からは人文学部と外国語学部が伝統的に支持され、そこに近年は流行の国際教養学部が台頭してきています。
近畿圏の関関同立には及びませんが、中京圏・東海地区の在住で親元から大学に通わせたいと考えると、関関同立に近い学力を誇る南山大学の一択になるでしょう。
学力だけでなく、就職においても中京圏・東海地区の中では関関同立やMARCH出身者と対等の扱いにされていることが非常に多く、関東と関西を除けば比べる相手がいないくらい南山大学の評価は高いです。
<立命館アジア太平洋大学>

立命館アジア太平洋大学は、2000年に創立された比較的新しい大学で、大分県の別府にキャンパスを構えています。京都の立命館大学と兄弟校です。
国際色豊かな大学で、秋田にある公立の国際教養大学と同様に学生の半数は留学生です。大分の大学内にいながら世界中の留学生と交流できることから、国内で留学しているような学生生活を味わえます。国際教養大学とは学術交流の提携を結んでいます。
サステナビリティと観光を合わせた「サステナビリティ観光学部」が注目されています。新しい国際社会を構築することを視野に入れながら観光の学習もできる学部で、将来は多方面で活躍できる人材が育っていくと考えられます。
また、広くアジアと太平洋に接する日本について学び、同時に諸外国のことを学ぶ「アジア太平洋学部」とグローバルなビジネスを勉強する「国際経営学部」も有し、大分県では国立の大分大学と包括的な提携を結んでいます。
語学に強い国際基督教大学、早稲田大学国際教養学部とも交流協定を結ぶなど、急速に知名度も上がってきています。
入試においては当然ながら英語力が問われます。他の大学とは試験の形式や内容もやや異なる所があるため一概に他の大学とは比べられませんが、英語を中心に高い学力が求められているのは間違いありません。
地方vs関東・関西、レベルの差は?
では、ここで全国の私立大学で難易度を上から順に見て、地方の大学がどれくらい入っているのかをご覧ください。
実際のところ、ほぼ関東圏と関西圏で占められており、50校まで調べても依然として地方の大学が見当たりません。つまり、大学の絶対数からして関東圏と関西圏が圧倒的に多いということです。
今回は中京圏・東海地区は地方に数えています。もし中京圏・東海地区を大都市圏として関東・関西と同列に扱うと、もう比較する表を作る自体に意義を感じないくらいです。
なお、下の一覧には芸術系の大学を除いています。
<私立文系の大学で平均偏差値の高い大学50校>
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 都道府県 (主なキャンパス) |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 慶應義塾大学 | 東京 |
| 2 | 69 | 早稲田大学 | 東京 |
| 3 | 67 | 国際基督教大学 | 東京 |
| 4 | 65 | 上智大学 | 東京 |
| 5 | 64 | 明治大学 | 東京 |
| 6 | 63 | 立教大学 | 東京 |
| 6 | 63 | 青山学院大学 | 東京 |
| 7 | 62 | 同志社大 | 京都 |
| 8 | 61 | 法政大学 | 東京 |
| 8 | 61 | 中央大学 | 東京 |
| 10 | 59 | 学習院大学 | 東京 |
| 10 | 59 | 関西学院大学 | 兵庫 |
| 12 | 58 | 立命館大学 | 京都 |
| 12 | 58 | 関西大学 | 大阪 |
| 14 | 57 | 成蹊大学 | 東京 |
| 14 | 57 | 日本女子大学 | 東京 |
| 14 | 57 | 国学院大学 | 東京 |
| 14 | 57 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分 |
| 17 | 56 | 明治学院大学 | 東京 |
| 17 | 56 | 武蔵大学 | 東京 |
| 20 | 56 | 東洋大学 | 東京・埼玉 |
| 20 | 56 | 成城大学 | 東京 |
| 20 | 56 | 南山大学 | 愛知 |
| 20 | 56 | 関西外国語大学 | 大阪 |
| 20 | 56 | 獨協大学 | 東京 |
| 25 | 55 | 駒沢大学 | 東京 |
| 25 | 55 | 近畿大学 | 大阪 |
| 25 | 55 | 中京大学 | 愛知 |
| 25 | 55 | 名古屋学芸大学 | 愛知 |
| 25 | 54 | 専修大学 | 東京 |
| 29 | 54 | 京都産業大学 | 京都 |
| 29 | 54 | 日本大学 | 東京 |
| 29 | 54 | 東京女子大学 | 東京 |
| 32 | 53 | 大和大学 | 大阪 |
| 32 | 53 | 津田塾大学 | 東京 |
| 32 | 53 | 西南学院大学 | 福岡 |
| 32 | 53 | 甲南大学 | 兵庫 |
| 32 | 53 | 神奈川大学 | 神奈川 |
| 37 | 52 | 龍谷大学 | 京都 |
| 37 | 52 | 名古屋外国語大学 | 愛知 |
| 38 | 52 | 昭和女子大学 | 神奈川 |
| 38 | 52 | 二松学舎大学 | 東京 |
| 38 | 52 | 同志社女子大学 | 京都 |
| 41 | 51 | 京都女子大学 | 京都 |
| 41 | 51 | 愛知大学 | 愛知 |
| 41 | 51 | 東京経済大学 | 東京 |
| 41 | 51 | 東海大学 | 神奈川 |
| 45 | 50 | 産業能率大学 | 神奈川 |
| 45 | 50 | 文教大学 | 埼玉 |
| 45 | 50 | 玉川大学 | 東京 |
| 48 | 49 | 京都外国語大学 | 京都 |
| 48 | 49 | 武庫川女子大学 | 大阪 |
| 48 | 49 | 大東文化大学 | 東京 |
| 48 | 49 | 聖心女子大学 | 東京 |
以上のようになりました。
同じ文系といっても、もっぱら語学に強い所や、様々な学部それぞれのレベルが高い所、コンピュータを多様して理系の要素も採り入れた総合タイプの所、教員養成に伝統と実績を持つ所など、学校によって全然違います。
また近年は、 どの学部というより公務員試験の合格者が多いことをアピールする大学が増えるなど、時代の変化が見受けられます。
そのため、単に入試の難易度を見ても、それをもって入学後の学習が異なる大学同士を比べてどちらがいいとかダメとかの話にはなりません。
いずれにしても、地方の大学は何らかのアピール材料を用意して知名度を上げる、あるいは地元の国公立大学と学術交流をして研究活動レベルを上げる、地元の企業から協力を得て就職などにも強くなる、などの方策が求められます。

<地元では有名な地方の有力大学>
ここで、全国的には知られていなくても、その地方にいる人なら皆が知っている、という地元の有力な大学群をご紹介します。
| 地方 | 大学名 |
| 東北地方 | 東北学院大学 |
| 九州地方 | 西南学院大学 |
| 東海地方 | 南山大学 |
| 北海道地方 | 北海学園大学 |
| 中国地方 | 広島修道大学 |
以上の大学で「東西南北広」と呼ばれることがあります。
宮城県仙台市の東北学院大学「東」、福岡県福岡市の西南学院大学の「西」、愛知県名古屋市の南山大学の「南」、北海道札幌市の北海学園大学の「北」に加えて、近年に広島県広島市の広島修道大学が加わり、全国各地の有力私立大学の大学群としてまとめて「東西南北+広」と呼ばれます。
東北学院大学、西南学院大学、南山大学はキリスト教にルーツを持つ大学で、昔から語学教育には定評がありました。英語に強いので、入試でもその地方の中では高い難易度になります。
それぞれの地方では名の知られている大学ばかりです。有名で難易度もその地方においては高く、就職も強い。そうなると地方の有力な大学となるのは当然です。
就職の評価が高い地方私立大学(文系編)
<前橋国際大学>

前橋国際大学は一学年の学生数が200人ほどの小規模の大学で、群馬県の前橋にキャンパスを構えます。
学部は「国際社会学部」で、英語コミュニケーションコース、国際コース、情報・経営コース、心理・人間文化コースがあります。2026年には幼児教育・保育コースが開設される予定です。
さらに、新設の学部でデジタル共創学部も2026年に開設される予定です。
開校は1999年で比較的新しく、そのため知名度はあまり高くありませんが、大学を開設して間もなく改革に着手し、それが功を奏して群馬県に本拠を置く私立大学の中では一躍人気校に成長しました。
例えば英検2級など大学が指定する資格があれば授業料全額免除などの思い切った制度を採用しPR活動を繰り広げ、それに伴って志願者、入学者が増えていきました。このような資格特待生制度は、単に授業料が安く済むだけでなく、受験生にとっては頑張って取得した資格を活かして入学できるというメリットがあります。
この資格を更に活かして、2級から準1級へ、そして1級まで目指せるという大学4年間の新たな目標ができます。とりあえず大学へ、というやや無目的な学生が多い中、意義のある資格取得に取り組み、やがては就職活動でも大きな武器になるのは非常にやり甲斐を感じることでしょう。
入試の難易度で選ばれる大学という位置づけでは、学力の高くない大学には有能な学生が集まりにくいのが現状です。そこを、資格を活かして入学できて、資格をさらに伸ばして学生生活を送れる、というのは大学選びの新しい基準になり得ます。
また、入学した学生たちもアンケートで「入学してよかった」と答えた人が8割を超えるなど、満足度が高いのも特徴です。
<北海道武蔵女子大学>

北海道武蔵女子大学は、前身の武蔵女子短期大学から新たに創設された、札幌の都心部付近にある大学です。
1967(昭和42)年、女子の高等教育を行う短期大学を開設したいとの思いから、少人数制教育に強みを持つ東京・武蔵大学の同窓有志と地元有志により北海道武蔵女子短期大学が開学されました。
それ以降、堅実で自立した社会人を育成する定評があり、「就職の武蔵」というキャッチフレーズで知られるようになりました。北海道内の女子の短大としては就職率96%〜97%の強い実績と伝統があり、それが4年制大学へと移行し、道内企業の要請にも見合った進化を遂げようとしています。
新設の北海道武蔵女子大学は、経営学部・経営学科のみの単科大学です。短期大学部には教養学科、英文学科、経済学科の3学科がありましたが、そのうち経済学科を四年制大学に改組して経営学部・経営学科となりました。
学内の勉強は、課題解決型学習(PBL)にも力を入れ、経営は勿論のこと、情報やデザインも学べるなど将来の女性管理職の登用に対応可能なカリキュラムが用意されています。
語学教育は英語を中心に、中国語や韓国語も学習できるようにするなど幅広い展開が期待されています。
また、実際に企業に行き、実習する企業研究プログラムなど職業体験も充実し、ビジネスマナーも勉強できるのが短期大学時代からの伝統的な強みです。企業実習から就職へ、という就職支援制度が手厚いことでも知られ、資格取得の講習や模擬面接の演習なども受けられます。
まとめ
今回は、「文系編・評価が高い地方の私立大学とは?マナビバ調査!」のテーマで書き進めました。
その大学の所在地が少ない人口の地域の場合、生活圏内や通学圏内から入学者を集めるのは難しく、必然的に人口の多い地域にキャンパスを構えることになります。
その点で、「地方」の中の中核都市には少なからず大学があります。都会の代表である首都圏、関西圏、中京圏の「三大都市圏」はモチロンですが、それ以外でも中国地方の広島、東北地方の仙台、九州地方の福岡、北海道地方の札幌などは大学が多くある都市と言えます。
ここに、四国の高松と松山、九州の熊本、北陸の金沢と新潟あたりに大学が増えるよう国の政策として支援があれば、大都市ばかりに大学が集中せずに緩やかに分散することができるかも知れません。
あるいは、中国地方で近畿圏に隣接する岡山や、中京圏と関東圏の間の静岡なども大都市の大学のキャンパスの一部を拡充して設置する、などの方策も考えられます。
現状として、大学に行きたくても行けない地域に住んでいる人々が不遇で、何らかの活路を見出す必要があるのは確かです。ネットによる通信教育の普及なども一考の価値があります。ただ、ネット教育では地方にキャンパスを構えるという話とは違ってきます。
「文系」の大学は、「理系」の大学ほどの研究施設の費用はかかりませんが、国の補助が大きい国公立大学とは違い、「私立」の大学で「地方」にキャンパスを構えるには、何らかの魅力や実利がなければ太刀打ちできません。
これからの「地方」で私立大学がどうやって人気を集め、ひいては難易度またはそれに代わる指標で学生を集めていくのか知恵を出し合う機会が求められます。
地元の企業や自治体も地元の若者を採用するのが圧倒的に多い訳ですから、充実した勉学と学生生活を送れる私立大学が地元にあれば助かります。